| ぜんそくの治療は発作時と発作予防の二つに分けられます。発作は命にかかわる危険な場合もあり、速やかな治療がとても重要です。それほど重くない発作でも早く楽にしてあげたいというのがご両親の願いでしょう。 ぜんそくの発作は夜に悪化することが多いので、あらかじめ発作時の飲み薬や吸入薬、張り薬などをもらっておくと良いでしょう。それらの薬を使っても、苦しくて眠れない、食べ物を受け付けないといった症状が続く場合には速やかに受診する必要があります。 何度も発作を起こす場合には発作を治すだけではなく、予防する治療が必要になります。ぜんそくの治療は“アレルギー性炎症”を抑えることが重要で、成人では炎症を抑える作用が最も強力な吸入ステロイド薬が主な治療法です。この薬の副作用を心配される方も多いのですが、小児での安全性も認められています。日本小児アレルギー学会の小児ぜんそく治療ガイドラインでは、年長児のぜんそく予防治療には早期からの吸入ステロイド薬使用が推奨されています。  ステロイド以外にはインタール吸入薬やロイコトリエン拮抗(きっこう)薬(オノン、シングレア、キプレス)、テオフィリン製剤(テオドール、テオロングなど)が発作予防に用いられます。いずれも炎症を抑える作用を持つ薬剤であり、これらの予防薬の中からそれぞれの子にあった薬剤を選択し、時には組み合わせて使います。 ステロイド以外にはインタール吸入薬やロイコトリエン拮抗(きっこう)薬(オノン、シングレア、キプレス)、テオフィリン製剤(テオドール、テオロングなど)が発作予防に用いられます。いずれも炎症を抑える作用を持つ薬剤であり、これらの予防薬の中からそれぞれの子にあった薬剤を選択し、時には組み合わせて使います。発作時に用いられる吸入薬(ベネトリン、メプチンなど)は一時的に呼吸を楽にする効果はありますが、炎症を抑える作用はないので発作が多いときは必ず予防薬と併用します。 日常生活の注意点としては、ほとんどのぜんそく児はハウスダスト、チリダニにアレルギー反応をもっていますので、日常の掃除などダニ対策が大変重要です。しかし多くの場合、高価な防ダニ寝具や器具を買いそろえる必要はありません。毎日の服薬や発作の状態を記録するぜんそく日誌も、より良い治療法の選択や生活指導を行う上で欠かせません。 適切な予防治療を継続することにより、ぜんそくの子どもたちの多くは、健康児と何ら違いのない生活を送れるようなります。発作のない状態を維持することが“ぜんそくを治す”ことにもつながるのです。
|
 皮膚を清潔に保つには、手を使って泡立てたせっけんでやさしく洗います。きれいにしようとしてタオルやガーゼでこすり過ぎるとかえって悪くなります。洗った後はすばやくワセリンなどの保湿剤を塗って皮膚の水分を保ちます。湿疹が悪化したときは、適切な強さのステロイド軟こうで炎症を抑える必要があります。副作用を心配される方がいますが、使用方法が適切であれば心配はありません。かゆみが強いと無意識に引っかいて湿疹を悪化させるので、かゆみを抑えるような飲み薬をうまく利用することも重要です。
皮膚を清潔に保つには、手を使って泡立てたせっけんでやさしく洗います。きれいにしようとしてタオルやガーゼでこすり過ぎるとかえって悪くなります。洗った後はすばやくワセリンなどの保湿剤を塗って皮膚の水分を保ちます。湿疹が悪化したときは、適切な強さのステロイド軟こうで炎症を抑える必要があります。副作用を心配される方がいますが、使用方法が適切であれば心配はありません。かゆみが強いと無意識に引っかいて湿疹を悪化させるので、かゆみを抑えるような飲み薬をうまく利用することも重要です。 最近、口腔(こうくう)アレルギー症候群(OAS)が問題になっています。これはリンゴやモモなどの果物や野菜を食べると、口内やのどがかゆくなり今まで食べていた食物が食べられなくなる病気です。OASのほとんどはシラカバなどの花粉アレルギーが原因で、鼻炎や結膜炎の症状を起こすようになった後、何年もたってから症状が出てきます。OASになると原因食物を生では食べられませんが、ジャムやジュースなどの加工品は食べられます。
最近、口腔(こうくう)アレルギー症候群(OAS)が問題になっています。これはリンゴやモモなどの果物や野菜を食べると、口内やのどがかゆくなり今まで食べていた食物が食べられなくなる病気です。OASのほとんどはシラカバなどの花粉アレルギーが原因で、鼻炎や結膜炎の症状を起こすようになった後、何年もたってから症状が出てきます。OASになると原因食物を生では食べられませんが、ジャムやジュースなどの加工品は食べられます。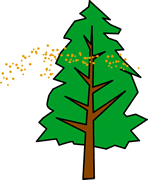 いままでアレルギー性鼻炎は大人になってからなる病気という印象があったのですが、最近では乳幼児期にも多い病気であることが分かってきました。子どもは、気管支ぜんそくがあるとアレルギー性鼻炎も一緒に起こしていることが多く、2001年に北海道小児喘息(ぜんそく)研究会が道内4千人以上の小児ぜんそくの患者さんにお願いしたアンケート調査では、50%の患者さんがアレルギー性鼻炎になっていました。
いままでアレルギー性鼻炎は大人になってからなる病気という印象があったのですが、最近では乳幼児期にも多い病気であることが分かってきました。子どもは、気管支ぜんそくがあるとアレルギー性鼻炎も一緒に起こしていることが多く、2001年に北海道小児喘息(ぜんそく)研究会が道内4千人以上の小児ぜんそくの患者さんにお願いしたアンケート調査では、50%の患者さんがアレルギー性鼻炎になっていました。 川崎病の主な症状を挙げると、[1]40度近くの発熱があります。多くの場合5日以上続きます[2]体にいろいろのタイプの発疹(ほっしん)がみられます。BCGの注射部位が赤くなるのが特徴的です[3]手足に発赤やはれができます。皮膚がテカテカとむくみ、回復期にはつめとの境目から膜状に皮膚がはがれます。川崎病に特徴的です。
川崎病の主な症状を挙げると、[1]40度近くの発熱があります。多くの場合5日以上続きます[2]体にいろいろのタイプの発疹(ほっしん)がみられます。BCGの注射部位が赤くなるのが特徴的です[3]手足に発赤やはれができます。皮膚がテカテカとむくみ、回復期にはつめとの境目から膜状に皮膚がはがれます。川崎病に特徴的です。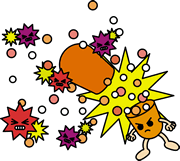 γグロブリンとは、私たちの血液中に多量に含まれている免疫グロブリン(抗体)のことで、感染から体を守る大切なものです。以前はアスピリンという熱冷ましの薬を使う治療でしたが、1984年にγグロブリンの併用が川崎病に有効であることが分かり、治療に関して大きな進歩がありました。
γグロブリンとは、私たちの血液中に多量に含まれている免疫グロブリン(抗体)のことで、感染から体を守る大切なものです。以前はアスピリンという熱冷ましの薬を使う治療でしたが、1984年にγグロブリンの併用が川崎病に有効であることが分かり、治療に関して大きな進歩がありました。 一方、大人になってから、川崎病にかかる人が極めて少ないことで、大人は自然に免疫を獲得していると推測されます。これらの事実を考え合わせると、川崎病の発症に「感染」がなんらかの形で強くかかわっていると考えられています。
一方、大人になってから、川崎病にかかる人が極めて少ないことで、大人は自然に免疫を獲得していると推測されます。これらの事実を考え合わせると、川崎病の発症に「感染」がなんらかの形で強くかかわっていると考えられています。 札幌市で来年から、年末年始などの休日当番医を増やす、新しい救急医療体制が始まります。小児科医だけで小児一次救急を受け持っている地区は、道内では札幌市や函館市など数カ所です。札幌の夜間救急センターは、土曜日、休日の午後7時−午前零時を小児科医2人で担当することにし、混雑緩和を図ろうとしていますが、小児科以外の医師の応援も必要になると思われます。
札幌市で来年から、年末年始などの休日当番医を増やす、新しい救急医療体制が始まります。小児科医だけで小児一次救急を受け持っている地区は、道内では札幌市や函館市など数カ所です。札幌の夜間救急センターは、土曜日、休日の午後7時−午前零時を小児科医2人で担当することにし、混雑緩和を図ろうとしていますが、小児科以外の医師の応援も必要になると思われます。 熱によるひきつけは、通常6カ月から5歳くらいまでの小児に発症します。熱は38度以上のことが多く、子どもの2〜4%は7歳ぐらいまでに一度は経験していると言われています。しばしば遺伝の傾向がみられ、家族歴があることが多いといわれております。ひきつけ自体は脳に障害を及ぼすことはなく、両親、きょうだいに熱性けいれんのある子は発症しやすいといわれています。
熱によるひきつけは、通常6カ月から5歳くらいまでの小児に発症します。熱は38度以上のことが多く、子どもの2〜4%は7歳ぐらいまでに一度は経験していると言われています。しばしば遺伝の傾向がみられ、家族歴があることが多いといわれております。ひきつけ自体は脳に障害を及ぼすことはなく、両親、きょうだいに熱性けいれんのある子は発症しやすいといわれています。 声がかれ、「犬がほえるような」「トドの鳴き声」と表現されるせきで、息を吸うときにぜんめい(吸気性ぜんめい)を伴うものには仮性クループ(喉頭蓋(こうとうがい)炎)があります。3〜4日ぐらい、夜になると症状が悪くなり、多呼吸や胸がへこむ陥没呼吸などの呼吸困難を伴うことがあるので、注意が必要です。
声がかれ、「犬がほえるような」「トドの鳴き声」と表現されるせきで、息を吸うときにぜんめい(吸気性ぜんめい)を伴うものには仮性クループ(喉頭蓋(こうとうがい)炎)があります。3〜4日ぐらい、夜になると症状が悪くなり、多呼吸や胸がへこむ陥没呼吸などの呼吸困難を伴うことがあるので、注意が必要です。